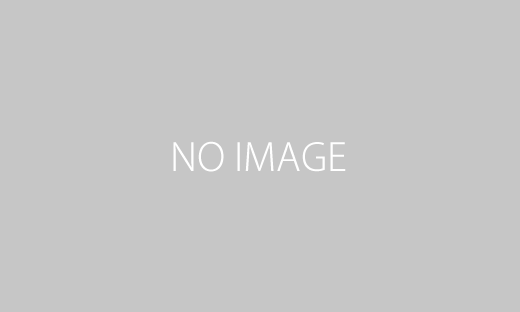労働者代表の選任方法には要注意~松山大学事件~
労使使協定(たとえば36協定)を結ぶ際には、労働者の過半数を代表する者を選ぶことが必要です。ところが、この「過半数代表者」の選任方法が公正でなければ、協定そのものが無効となる可能性がある点はあまり知られておらず、注意が必要です。
松山大学事件(最三小判 平成24年3月2日)では、大学が36協定を結ぶために職員から過半数代表者を選任したものの、その手続きが十分に民主的でなかったと判断され、協定の効力が否定されました。裁判所は「代表者は使用者の意向で一方的に決められるのではなく、労働者の自由な意思に基づいて選出される必要がある」と明確に示したのです。
この判例から、実務においては以下の点が特に重要です。
① 労使協定ごとに、選出方法を従業員へ広く周知し、公平な手続きで行うこと
② 多数決など民主的な方法で選出すること
③ 管理監督者を代表にしないこと
もし、以下のような場合は、すぐに選任方法の見直しをしましょう。
・社員の飲み会やイベントを企画する幹事が、労働者代表という慣例がある。労働者代表のサインが必要となる事案については、すべてどんな内容でも、その幹事にサインをもらうことになっている。毎年、社員たちの推薦で選んでいるので、問題ないだろう。
・常に事務所にいるのが、総務の社員だけなので、「はい、サインお願い」といって社長がサインを依頼している。
・社歴の一番長い人が労働者代表になるのが好ましいと思うため、その方にいつもサインをお願いしている。
過半数代表者の選任は、形式的な手続きを整えるだけでなく、従業員の信頼を得る過程そのものが大切です。正しく選ばれた代表と結んだ協定は、会社にとっても従業員にとっても安心して働ける基盤となります。
労使協定は、36協定以外にも、育児介護休業にかかる労使協定、1か月(1年)単位の変形労働時間制、フレックスタイム制にかかる労使協定、派遣労働者の同一労働同一賃金に関する労使協定、賃金控除に関する労使協定など、多岐にわたります。今一度自社の労使協定を確認しましょう。